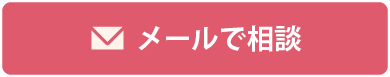相続改正法
改正相続法
2020年4月1日より全面施行されます。まず、2019年1月13日に自筆証書遺言の方式を緩和する法律が施行され、2020年4月1日に「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」が施行されました。
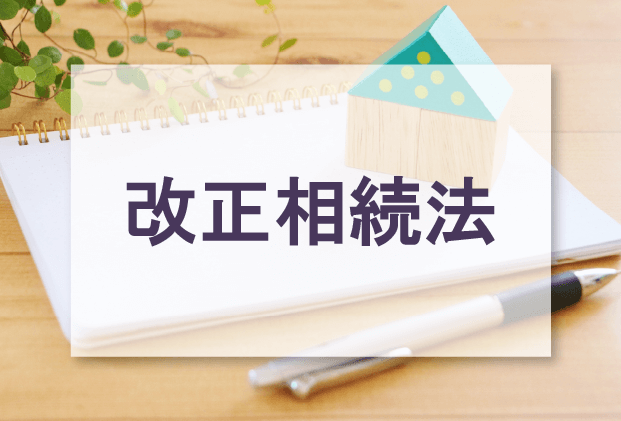
自筆証書遺言とは
遺言とは財産を持った人が亡くなる前にその財産を相続人などに、争族とならないよう財産を前もって誰に何を残すのかを書き残した文書を遺言と言います。 その遺言を自筆で書いたものを自筆証書遺言書と言います。
自筆証書遺言は改正前だと、その全文(内容、財産目録、日付、署名)を自筆で書き押印しなければなりませんでした。
民法968条1項
自筆証書遺言によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
上記のように改正前はすべてを自筆で書かなければならなく、遺言書を書いたのが本人(遺言者)なのかどうか確かめるために全文自筆とされていました。
なぜなら、遺言の効力が発生するのが遺言者が亡くなった後だからです。
民法985条
遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
しかし、遺言を全て自筆にすると、遺言者の負担となり、財産目録や内容が多ければ多いほど書き間違いの原因にもなってしまいます。
また、内容が多ければ書くのが面倒となり書かずに亡くなってしまう事もあり、書いておいても書き間違いにより遺言執行ができないなど問題が多くありました。
こういった背景があるため、自筆証書遺言の緩和する法律が施行されました。
自筆証書遺言の緩和内容
遺言内容の全部を自筆とすると遺言者の負担が大きい為、一部(財産目録のみ)を自筆でなくても構わないと緩和されました。
民法968条2項
前項(968条1項)の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
上記の通り自筆証書遺言の財産目録は自筆でなくてもよくなりました。
では、どういったもので対応が可能になったかというと
- パソコンなどにより作成された財産目録
- 預金通帳の写し
- 不動産などはその登記事項証明書
自筆証書遺言の緩和の注意点
自筆で書かなくていいのは財産目録のみになります。
財産目録を自筆証書遺言に添付する形のみ認められます。要は1ページに自筆で書いた内容と通帳などの写しを張り付けたりし自筆と自筆でないものを混在させて作成する事はできません。
また、財産目録にはそれぞれ署名と押印が必要になり3ページにわたる財産目録があった場合には、3ページともに署名押印をしなければなりません。
これは、悪意ある相続人が財産目録を差し替えたりするのを防止するためのものです。
※両面印刷などにより裏表に財産目録を印刷などした場合には、裏表それぞれに署名押印をしなければなりません。
「配偶者居住権」「配偶者短期居住権」とは
少子高齢化が進んで平均寿命も延び、夫婦の一人が無くなってしまった場合に残された一方が長い期間生活していかなければならない事も多くなってきました。
そこで、残された一方が今まで住んでいた住居に賃料などの負担が無く、住み続けながら生活資金として預貯金なども相続できるようにした制度が「配偶者居住権」になります。
この配偶者居住権には期限はなく原則として終身とされている。
これに対し、「配偶者短期居住権」は遺産分割協議により建物の所有者が確定するまで、もしくは相続開始を知った時から半年を経過する日のどちらか遅い日までとなります。
また、建物の所有権が第三者が取得した場合もしくは配偶者が相続の放棄をした場合には、所有権を取得した人が短期居住権の消滅を通知すれば配偶者はその通知を受け取った日から半年を経過するまでは無償で住居を使用できるとされています。

配偶者居住権の注意点
この「配偶者居住権」に関しては遺産分割協議の選択肢として配偶者が取得でき、遺言によって配偶者居住権を取得させることもできます。遺言による配偶者居住権は配偶者が遺贈を受ける建物に遺贈者が亡くなった時点でも居住している事が必要です。
また、この「配偶者居住権」は登記をすることによって効力を発するので必ず設定登記が必要となります。
※2020年4月1日以前にされている遺言に関しては配偶者居住権を取得・設定する事はできないので注意が必要です。

記事監修
借地権や底地で様々な悩みを抱えている方々へ!
その悩み解決します。
監修者
株式会社マーキュリー 取締役 大庭 辰夫